
ブロッコリーの特徴
ブロッコリーは、別名イタリアン・ブロッコリーと呼ばれています。
地中海沿岸の野生のキャベツを改良したものであり、頭頂部のつぼみと茎を食べています。
原産地は地中海沿岸。
イタリアで改良されてヨーロッパ中に広がり、日本では明治時代に伝わりましたが、当初は観賞用とされていました。
本格的に広まったのは戦後からで、アメリカから輸入物が入ってくるようになってから急速に出回っていきました。
ブロッコリーは、料理に映える鮮やかなグリーン色が魅力。
味や香りにクセがなく、ほのかな甘味があることから、どの年代にも人気です。
栄養価の高い緑黄色野菜として需要が高くなっています。
ブロッコリーに含まれる栄養素の多くは水溶性。
水につけると溶け出してしまうものばかりなので、栄養をより多く摂取したいのであれば、短時間で調理する必要があります。
また、ブロッコリーはとても鮮度が落ちやすい野菜。
たった3日経っただけで、ビタミン類の栄養価やうま味が半分くらいにまで減ってしまうので、購入後はできるだけ早く使い切るほうがいいでしょう。
ブロッコリーは、くせのない野菜で、どんな調理法にでも合います。
サラダや炒め物・煮込み料理など、いろいろな料理に使われていますが、チーズとの相性もよく、グラタンやピザに加えても美味しいです。
調理するときは、枝分かれしている房を、なるべくくずさないように切り分けましょう。
また、茎に切り込みを入れて手で割ってもいいです。
ブロッコリーをシチューなどに入れる場合は、ほかの具材といっしょに煮込まず、別にゆでたものを最後に加えたほうがいいでしょう。
ドレッシングや酢などを使うときは、酸の働きで色が変わってしまうので、すぐに食べましょう。
蒸し器で蒸すと栄養の損失が軽減されるうえ、色鮮やかに仕上がります。
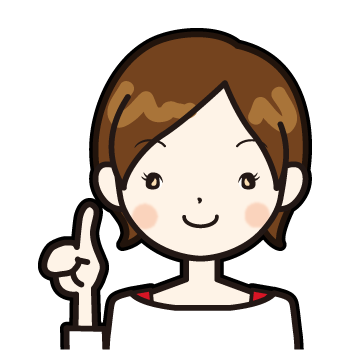
ただ、茎の部分はクセが少なく、食物繊維などの栄養が豊富に含まれているので、食べることをおすすめします。
厚めに皮をむいて薄切りにし、塩ゆでや炒めものに加えたり、浅漬けやピクルスになどにすると美味しいです。
ブロッコリーのゆで方
ブロッコリーのゆで方ですが、フライパンにブロッコリーと塩ひとつかみを入れます。
半分つかるくらいの水を注いで強火にかけ、ふたをして3分ほどでできあがりです。
長くゆでると、ビタミンCなどの栄養素が逃げやすいので注意しましょう。
ゆでた後は、水にとらないでください。
水にとると、味や香りが損なわれるので、ざるに広げて手早くさましましょう。
ブロッコリーの種類
| 茎ブロッコリー(スティックセニョール) | |
|---|---|
| 茎の部分が長く、味がアスパラガスに似ています。
細かく分ける手間がはぶけるので人気があります。 |
|
| 紫ブロッコリー | |
| アントシアニンを含むため紫色ですが、ゆでると色が溶け出し、緑色になってしまいます。 | |
ブロッコリーの旬
旬のカレンダー
![]()
ブロッコリーは、寒い地域のものが春先から出まわっていますが、美味しくなる旬は11月~3月。
ブロッコリーの産地
|
都道府県別収穫量(農林水産省 平成24年統計 参照) |
|---|
| 北海道 全国収穫の16.4%の構成比 22,600t |
| 愛知県 全国収穫の11.4%の構成比 15,700t |
| 埼玉県 全国収穫の10.8%の構成比 14,900t |
ブロッコリーの栄養価の高さが注目されるようになって、ここ10年で消費が拡大しました。
以前は夏季に輸入ものが出まわっていましたが、近年は北海道が夏場の産地として安定しているので、輸入量は減ってきています。
また、最近では、アメリカから輸入されているものが多くなってきています。
ブロッコリーの上手な選び方
- ずっしりと重さがあるもの。
- 先端がもりあがっていて、みずみずしいもの。
- 黄色くなっているものは選ばないほうがいいです。
- 鮮度が落ちると、茎の切り口が茶色く変色したり、乾燥しています。
- つぼみが開いたものは、苦味が出るので避けたほうがいいでしょう。</li>。
ブロッコリーの保存法
ブロッコリーは、新鮮なものほど甘みがあるので、できるだけ早めに食べたほうがいいでしょう。
冷蔵保存する場合は、湿らせたキッチンペーパーで切り口を包み、ポリ袋に入れ、立てて保存してください。
冷凍保存する場合は、かために塩ゆでし、小分けにします。
かためにゆでておくと、1か月位は保存可能です。
【ブロッコリーのカロリーや栄養はコチラ】
▶▶▶ブロッコリーのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介
