
なすの特徴
なすの原産地はインドで、日本には8世紀ごろ中国から伝わってきました。
日本だけでも180種類以上、世界では約1000種類もあり、品種はとても多いです。
なすは、「成す」・「生す」という言葉を思わせ、昔から縁起の良い野菜として親しまれてきました。
奈良時代から全国に広まり、丸型・卵型・長型・紫・白・緑等、形や色はさまざまですが、現在では地域による特徴のある品種が栽培されています。
なすには、「秋茄子は嫁に食わすな」ということわざがあります。
体を冷やす野菜なので、赤ちゃんを産むお嫁さんを気遣っているという意味と、美味しいので食べさせないという2つの解釈があります。
なすは、炒めものや天ぷら・焼きなす・煮物・グラタンなど、なんにでも使うことができる万能野菜。
油との相性がよく、揚げたり炒めたりすることで甘みが増します。
ただ、油をよく吸うので、ダイエット中の人は避けたほうがいいでしょう。
また、味噌との相性もいいので、田楽やみそ汁などにしても美味しいです。
みそ汁の具にする場合は、煮すぎるとやわらかくなり色や味が悪くなるので、軽く火が通ったところで仕上げるのがおすすめです。
なすは、冷蔵庫から出すと、汗をかいたような水滴がついているので、室温で少し置いてから使いましょう。
紫色の皮にもっとも体にいい成分が含まれているので、皮はむかずに食べるのが理想的になります。
なすを揚げるときは、小さく切り分けず、揚がった後に熱湯をかけて油切りをすると、余分な油脂分をカットすることができます。
加熱すると、うま味成分であるグアニル酸が増えますが、丸ごと加熱したほうがグアニル酸の量はアップします。
なすを切る時ですが、なすは皮がかたくそのままでは味が染み込みにくです。
見た目も考えると、斜めや格子状に包丁を入れるほうがいいでしょう。
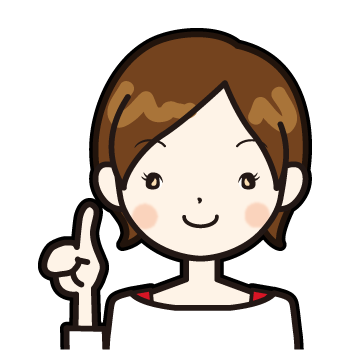
鍋焼きグリルで、全体が均等に黒く焦げるまで焼きます。
その後、流水に取って手で皮をむくとよく、焼きなすの皮をむいてラップで冷凍保存すると、1ヶ月位はもちます。
アク抜きは水にさらすか塩をふる
なすは、切ったらすぐに調理するか、水にさらしておかないとすぐにアクが出て変色してしまいます。
すぐに調理しない場合はアク抜きを忘れずに行う必要があります。
アク抜きは、水にさらすか、塩をふって水分を出すといいでしょう。
水を張ったボウルにナスを入れ、ペーパータオルなどで水分をふき取って調理すると、水っぽくならないです。
なすの種類
| 千両なす | |
|---|---|
| 全国的に最も多く生産されているなす。 漬物や焼きなす・煮物と、調理の種類が多く人気があります。 |
|
| 水なす | |
| 生食が可能ななすは全国的に珍しく、通常のなすより丸みを帯びていて水分が多い。
甘みがあり、アクも少ないので生食が可能になっています。 大阪の泉州地方で特に盛んに栽培されています。 |
|
| 米なす | |
| アメリカ産の品種を改良したもので、ヘタが緑色をしているのが特徴。
果肉が締まっていて、煮物や揚げ物などの加熱調理に向いています。 |
|
| 小なす | |
| 甘みがあり皮がやわらかくタネも少ないので、おもに漬物用になっています。 | |
| 長なす | |
| やわらかい果肉で、やや水っぽいのが特徴。
西日本で一般的であり、焼きなすや炒めもの・田楽に向いています。 |
|
| 巾着なす | |
| 果肉がかたく締まっていてかためなので、加熱してもくずれにくいのが特徴。 | |
| 白なす | |
| 果肉がやわらかであり、加熱するとトロリとした食感になります。 | |
| 十全 | |
| 新潟県の夏の風物詩であり、漬け物にすると絶品の丸型小なすになります。 | |
| 赤なす | |
| 通常のなすの3倍ほど大きく、肉質はやわらかくタネもアクも少ない。 | |
| 青なす | |
| 緑色の果皮の品種であり、果肉は加熱するとやわらかくなります。 | |
| 賀茂なす | |
| 京都の上賀茂地域で栽培。
やわらかくて甘みがあり、田楽・揚げ物に向いています。 |
|
なすの旬
旬のカレンダー
![]()
なすは、ハウス栽培を中心に一年中出回っていますが、旬は夏。
なすの産地
|
都道府県別収穫量(農林水産省 平成24年統計 参照) |
|---|
| 高知県 全国収穫の9.7%の構成比 31,900t |
| 熊本県 全国収穫の9.3%の構成比 30,600t |
| 群馬県 全国収穫の7.1%の構成比 23,200t |
7月から11月にかけて出まわる夏秋なすは、露地もの。
茨城・栃木・群馬といった、主に都市近郊で栽培されています。
12月から6月にかけて出まわる冬春なすは、高知や熊本・福岡といった、暖地のハウスなどの施設で生産されています。
なすの上手な選び方
- 表面にシミや傷がないもの。
- ずっしりと重みがあるものは水分が多いです。
- 皮の色が濃く、ハリとツヤがあるもの。
- ヘタがしっかりとし、とげが鋭くとがっているもの。
- 皮に傷があるものは避けたほうがいいでしょう。
ヘタは鮮度を見分ける方法の一つ。
ただ、鋭いトゲが生えていて、刺さって怪我をすることがあるので、注意する必要があります。
なすの保存法

なすは低温に弱いので、紙袋に入れた後、風通しの良い涼しいところで保存したほうがいいです。
冷蔵庫で保存する場合は、ポリ袋に入れた後、新聞紙で包み、野菜室などに入れます。
ただ、冷えすぎると、皮やタネがかたくなってしまうので、早めに食べましょう。
冷凍保存する場合は、ヘタとガクを取ってから縦2等分に切り、ラップで包みます。
食べるときは、お好みの大きさに包丁で切るといいでしょう。
そのまま、炒めものやナムル・和え物などに使うことができます。
また、かたくて切りずらいときは、常温で少し解凍すると切りやすくなります。
【なすのカロリーや栄養はコチラ】
▶▶▶なすのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介
