
キャベツの特徴
キャベツは、ヨーロッパが原産。
古代ギリシャ・ローマ時代から食べられている最古の野菜の一つになります。
その時代のキャベツは今のように丸くはなく、葉はケールのように肉厚でした。
しかし、栽培の長い歴史の中で、現在のように丸く結球したものが誕生しました。
キャベツは、江戸時代に伝わりました。
最初は観賞用としての野菜だったのですが、明治時代以降栽培されるようになりました。
青汁の材料として使われているケールですが、南ヨーロッパが原産。
キャベツの祖先であり、花を食べるブロッコリーやカリフラワーもキャベツの親戚になります。
キャベツは周年流通していますが、春に出まわる春キャベツ・冷涼地で栽培される夏キャベツ・寒玉ともいわれる冬キャベツに分けられています。
春キャベツは、内部まで黄緑色を帯びてみずみずしくやわらかいので、生食に向いていて、浅漬けやスープの具などにすると美味しいです。
冬キャベツは、加熱してもくずれず、甘みが増して風味がでるので、煮込み料理に向いています。
ふんわりとみずみすしい春キャベツと、加熱すると甘みが増す冬キャベツでは、歯ざわりや風味がまるで違うので、それぞれの旬に合わせた調理法で味わうほうがいいでしょう。
キャベツは、生でも美味しく食べることができる、煮てよし、炒めてよしの万能野菜。
ロールキャベツやサラダ・酢の物・和え物・煮物・炒めもの・シチュー・スープなど、さまざまな料理に使われています。
キャベツは、切り分けると空気にふれる面が増えて鮮度が落ちやすくなってしまうので、葉を1枚ずつはがして使ってください。
芯はかたいのでカットするかそいで調理したほうがよく、キャベツの一番外側の大きな葉は固くて苦味も強いので、避けて食べたほうがいいでしょう。
キャベツには、うま味成分のグルタミン酸が豊富に含まれていて、煮込み料理にするとうま味が増します。
ソーセージやベーコン・豚肉と相性がよく、ロールキャベツにしたりやわらかく煮ると、甘みがでて美味しいです。
キャベツの千切りは、食物繊維が多いです。
トンカツなど、揚げ物の料理の横にキャベツの千切りなどがよく添えてありますが、キャベツは消化を促進する働きがあるので、効果的な食べ合わせだといえます。
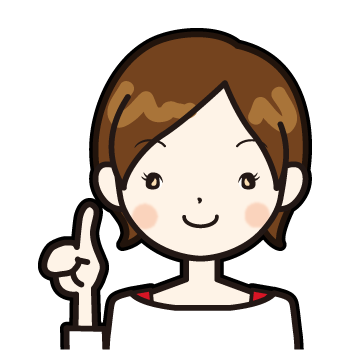
まず、葉っぱを1枚ずつていねいにはがし、葉っぱの真ん中にある筋を中心に重ねていきます。
芯に対して垂直になるように包丁を入れていくと、美味しくてふわふわした千切りがつくりやすくなります。
また、水にさらすと、千切りしたキャベツをパリッとさせることができます。
キャベツの種類
| 高原キャベツ | |
|---|---|
| 長野県野辺山や、群馬県嬬恋(つまごい)などの冷涼地で主に栽培されています。
春にタネをまき、夏から秋に出まわっています。 |
|
| 黒キャベツ | |
| ちりめんキャベツの系統で、結球しないタイプ。
繊維質で苦味もあるので生食には向かないですが、加熱すると美味しいです。 |
|
| 紫キャベツ | |
| 表面の鮮やかな色は、アントシアニンによるもの。
生で食べるとパリパリとした食感を楽しむことができます。 鮮やかな色を生かして、サラダやピクルスなどに利用されています。 |
|
| ちりめんキャベツ | |
| サボイキャベツとも呼ばれています。
フランスのサボア地方が発祥。 ちりめん状になった葉が特徴で、煮崩れしにくく日持ちします。 |
|
| 芽キャベツ | |
| ピンポン玉くらいの大きさで、やわらかく甘みがありビタミンCが豊富。
シチューなどの煮込み料理で使われることが多いです。 |
|
| たけのこキャベツ | |
| タネまきから3ヶ月ほどで収穫できます。
実がとてもやわらかいので生食に向いています。 |
|
| グリーンボール | |
| 形が丸く、春キャベツとは違い、巻きのかたい品種。
葉は鮮やかな緑色で、やわらかく生食に向いています。 |
|
| プチヴェール | |
| フランス語で「小さな緑」を意味するキャベツであり、芽キャベツとケールの交配種。
すぐれた栄養分を含み、甘く食べやすい味になっています。 |
|
キャベツの旬
旬のカレンダー
![]()
春キャベツは3月~5月・夏キャベツは7月~8月・冬キャベツは11月~3月が旬。
キャベツの産地
|
都道府県別収穫量(農林水産省 平成24年統計 参照) |
|---|
| 愛知県 全国収穫の18.2%の構成比 262,900t |
| 群馬県 全国収穫の18.0%の構成比 259,700t |
| 千葉県 全国収穫の8.9%の構成比 128,900t |
キャベツは収穫量第2位の野菜。
業務用の需要も安定しているため、周年供給できるように大規模な産地が多いです。
春キャベツは、海洋性気候で温暖な千葉県の銚子や神奈川県の三浦で生産。
夏キャベツは、群馬県の嬬恋(つまごい)や北海道など冷涼な地域で生産。
冬キャベツは、愛知県の東三河や、千葉県の海岸地帯などの暖かい地域で主に生産されています。
キャベツの上手な選び方
- 切り口がみずみずしいもの。
- 葉がしっかりと巻かれていて、重みがあるもの。
- 葉の色が濃く鮮やかでツヤとハリがあるもの。
- カットしたキャベツよりも、丸ごと1個購入したほうが鮮度が良いです。
- カットしたものを購入する場合は、身がよくしまっているものがよく、芯の高さが3分の2以下のものが良品です。
キャベツの保存法
キャベツは、芯の部分から傷んでしまうので、買ってきたら芯の部分を包丁で切り取ってしまうといいでしょう。
あとは、ラップに包んで冷蔵庫に入れると保存することができます。
カットしたものは、切り口をしっかりラップで包んでから保存しましょう。
葉を千切りにしてから冷凍すると、そのまま炒めものや解凍してコールスローなどに使うことができるので便利です。
【キャベツのカロリーや栄養はコチラ】
▶▶▶キャベツのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介
