
イカの種類と特徴
スルメイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
スルメ・マイカ
名前の由来
スルメというのは、本来はイカの干物のことでしたが、このイカが最も適していることから、スルメイカという名前がついています。
特徴
スルメイカは、スルメイカ科の頭足類であり、北海道から九州までの日本沿岸・千島・朝鮮半島に分布。
寿命は1年であり、その前半は成長・成熟のため北に回遊し、後半は交尾・産卵のため南に回遊。
日本で出荷されるイカの中で最も安価でなじみやすいイカのため、各地においてさまざまな形で食べられています。
夏に穫れるものを夏イカとも呼びますが、春から初夏に穫れる小ぶりのものをバライカといいます。
関東周辺では、麦が実る初夏頃に穫れる小さなイカをムギイカといいます。
世界のイカの消費量の約半分を日本だけで消費しているとされていて、その約半数はスルメイカといわれています。
スルメイカの旬は、7~9月。
スルメイカの産地は、北海道がもっとも多く全体の約3割を占めていて、その他は、青森県や石川県などが多くなっています。
栄養面では、良質なたんぱく質とビタミンB1・ビタミンB2が含まれています。
タウリンが豊富に含まれていて、疲労回復や血中コレステロール値を下げる働きが期待できます。
食べ方
スルメイカは、刺身や寿司・塩辛・一夜干し・干物など、さまざまな料理を楽しむことができます。
水洗いすると味が落ちるので、サッと中を洗う程度くらいのほうがいいでしょう。
肉厚な身を薄く2枚に切って細いそうめんにし、しょう油で食べるイカそうめんにすると、とても美味しい。
熱を通しすぎるとかたくなるので、8割がた火を通し、少し生っぽい位で切り上げましょう。
アカイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
ムラサキイカ・バカイカ
名前の由来
全体に赤みがかかっているから。
特徴
アカイカは、スルメイカ科の頭足類であり、津軽海峡以南・温帯域を中心とした世界の暖海に分布。
外洋性のイカであり、表層から水深1500mまでを泳ぎ回り、おもにハダカイワシ類・サンマ・イワシ類・イカ類などを食べています。
アカイカは開いて干したものがやわらかくて美味しい。
コウイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
ハリイカ・スミイカ
名前の由来
体内に甲(貝殻)を持っていることから。
特徴
コウイカは、コウイカ科の頭足類であり、本州中部以南の暖海から南シナ海・オーストラリア北部まで分布。
沿岸の砂泥底に生息し、夜行性で魚・甲殻類などを捕食。
5月頃内湾に集まり、長径1cmくらいの卵を1個ずつ海藻や沈木などに産みつけています。
コウイカの旬は産卵期の春から初夏にかけてであり、身が厚くて甘みがあり、寿司ネタに使われています。
食べ方
食べ方としてはやはり刺身が美味しく、独特の甘味とやわらかさをもっとも堪能できます。
ゲソは、甘辛く煮ると美味しい。
フライや天ぷら・中国料理の素材としても広く利用されています。
さばくのは少々難しいのですが、自分でさばくのなら、墨袋を破らないように細心の注意を払ったほうがいいでしょう。
ヤリイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
ササイカ・サヤナガ・テナシテッポウ・シャクハチイカ・ツツイカ
名前の由来
形が槍に似ていることから。
特徴
ヤリイカは、ジンドウイカ科の頭足類であり、北海道から南西諸島まで広く分布。
体長は雄で40cm・雌で30cmほどであり、産卵期は冬から早春で、沿岸の岩礁域の海藻や海底に数十粒の卵を産みつけます。
ヤリイカの旬は12月~3月頃で、上品で淡泊な味であり、寿司屋でしかでてこないような高級品です。
国内では人気が高いがあまり獲れないので、輸入物がほとんど。
アオリイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
アオイカ/バショウイカ(静岡)・アキイカ(京都)
名前の由来
半円形のヒレをあおって泳ぐ様子などから。
特徴
アオリイカは、ヤリイカ科の頭足類であり、北海道以南の日本沿岸からインド・太平洋域にかけての暖海に分布。
体長約40cmほどであり、大きな半円形のひれを持つのが特徴。
5~8月を中心とした産卵期には、沿岸の浅い岩礁域に移動し、卵を海藻に産みつけます。
アオリイカは、イカの中でもワンランク上の存在です。
旬は6月~8月ですが、ほぼ年間を通して安定した美味しさがあります。
食べ方
アオリイカの身は上品な味わいであり、程よい歯ごたえが楽しめます。
とろける甘みと噛むほどに広がるうま味を味わうには刺身が一番ですが、スルメなどにも加工されています。
さばくのは薄皮や皮をむくのに手がかかりやや難しいので、さばいてくれるところがあればさばいてもらうほうがいいでしょう。
ケンサキイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
ケンサキ、アカイカ、ブドウイカ、シロイカ/ゴトウイカ(九州)
名前の由来
胴の形を剣の先に見立てていることから。
特徴
ケンサキイカは、ジンドウイカ科の頭足類であり、相模湾および富山湾以南から九州・東南アジアからオーストラリア北部まで分布。
体長約25~40cmほどであり、産卵期は春から夏。
スルメは他のイカ類のスルメよりも上等とされていて、一番スルメとして珍重されています。
食べ方
刺身が美味しいですが、焼いても甘みが残りやわらかく、乾燥すると甘みがさらに増します。
ホタルイカの特徴
 別称・方言
別称・方言
コイカ・マツイカ(富山)
名前の由来
蛍のように発光することから。
特徴
ホタルイカは、ホタルイカモドキ科の軟体動物であり、日本海全域と北海道以南から土佐湾にかけての太平洋側に分布。
200~1000mの深海に生息し、全身に数百個の粒上の発光器があり、青緑色に発光するイカとして知られていてます。
ホタルイカの旬は産卵直前の4~5月であり、春から初夏にかけての産卵期には浅海に回遊しています。
食べ方
さっとゆでて、ショウガじょうゆで食べるのが一般的ですが、酢みそあえや串焼き・甘露煮などにしても美味しい。
沖漬け(醤油漬け)や燻製・みりん干し・缶詰などに加工されています。
イカの特徴

イカは種類が多く、全世界では約500種類あるともいわれています。
日本近海でも約100種類が生息しています。
日本で知られているものには、コウイカ・ヤリイカ・アオリイカ・ケンサキイカ・ホタルイカ・アカイカ・スルメイカなどがあります。
低カロリーであり、食べやすく価格が安いので、家庭では人気がある食材のひとつになっています。
実際の腕は8本で、残りの腕は触腕(しょくわん)と呼ばれていて、この触腕を伸縮させて獲物を捕獲します。
イカは、少し前までは、コレステロールが多い食材として認識されていました。
コレステロールの含有量は確かに多いのですが、同時にコレステロール値を下げるタウリンなども含まれているので、現在では気にする必要はないとされています。
イカの塩辛
 イカの塩辛は、細作りにしたイカの銅に塩をふり、イカのワタをあえたもの。
イカの塩辛は、細作りにしたイカの銅に塩をふり、イカのワタをあえたもの。
2~3日おくと、熟成が進んでいっそう美味しくなります。
居酒屋ではよく販売されていますが、酒のつまみとしてよく食べられている料理になります。
イカ飯
下足(げそ)を取り外し腹ワタを取り除いたイカの胴身に、洗った米を詰め込み醤油ベースの出し汁で炊き上げたもの。
デパートの催事(北海道展)などでよく販売されています。
スルメ
 スルメは、アタリメともいい、イカの内臓を取り除いて、素干しや機械で乾燥させた加工食品。
スルメは、アタリメともいい、イカの内臓を取り除いて、素干しや機械で乾燥させた加工食品。
長期保存に向いており、縁起物とされることもあります。
スルメは、「噛めば噛むほど味が出る」と表現されていますが、特に根拠はないです。
表面についている白い粉は、イカに含まれるアミノ酸が乾燥中にしみ出てきたものになります。
イカそうめん
 イカそうめんは、生のイカを細く切り、醤油やつゆで食べる料理。
イカそうめんは、生のイカを細く切り、醤油やつゆで食べる料理。
北海道、特にイカの水揚げで知られる函館の名産として紹介されることが多いです。
最近では、スーパーなどでパック詰めされた商品がよく売られています。
イカ焼き
 イカ焼きは、イカに醤油をつけてを丸ごと焼いている料理と、大阪で生まれたとされるイカを入れたクレープ状の料理の二種類が存在します。
イカ焼きは、イカに醤油をつけてを丸ごと焼いている料理と、大阪で生まれたとされるイカを入れたクレープ状の料理の二種類が存在します。
縁日などの屋台で販売されていることが多く、夏の風物詩として知られています。
イカの食べ方

イカは、生で食べる刺身のほか、煮てよし、炒めてよし、焼いてよしの万能食。
軟骨とくちばし以外は、ほぼ全てを使うことができます。
スルメイカは、刺身や寿司だね・煮物・フライなど、和洋問わず、どんなメニューにも向いています。
甘みが強いヤリイカ・硬い甲(かぶと)が特徴のコウイカ・甘みが強いヤリイカ・高級食材のアオリイカは、刺身や寿司だねに向いています。
小型であるホタルイカは、刺身はもちろん、ゆでて酢みそで和えたり、甘辛く煮込むと美味しいです。
水分を多く含むので、揚げるときは油はねに注意する必要があり、調理前には水気をふき取ってください。
加熱すると身が固くなるので、焼く場合は手早く調理するほうがよく、表皮は消化が悪いので、むいてから使うとほうがいいでしょう。
イカスミは、うま味成分に加えて脂質も含んでいてコクがあるので、パスタ料理に使うと美味しいです。
さといもと煮る時は、じっくり時間をかけて煮るとよく、中途半端に加熱するとかえって固くなります。
イカゲソとは、イカを食べるときの呼び名。
スーパーや居酒屋などで、天ぷらや唐揚げにして販売されています。
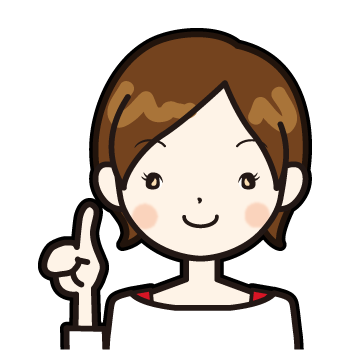
イカの皮は全部で4層あり、外側の1~2層は簡単にむけますが、3~4層はむきにくいので普通は残ってしまいます。
4層目の皮には非常に強い熱収縮性があり、収縮は縦方向に起こります。
ですから縦にぐるりと丸まってしまうのです。
イカの産地
|
農林水産省(平成24年漁業・養殖業生産統計) 参照 |
|---|
| 北海道 全国漁獲の26.0%の構成比 55,500t |
| 青森県 全国漁獲の24.1%の構成比 51,400t |
| 長崎県 全国漁獲の8.6%の構成比 18,400t |
イカは、日本各地に生息していますが、輸入物も多いです。
年間を通して漁獲されていますが、9~11月にかけて日本海の沖合を回遊するため、日本海側でよく穫れます。
日本で食べられている約80%はスルメイカ。
日本は世界で一番イカを食べていて、その消費量は世界の漁獲量のほぼ2分の1ともいわれています。
イカは、全世界の浅い海から深海まであらゆる海に生息しています。
漁法としてはイカ釣り漁船によるものがあり、集魚灯に集まったところを自動イカ釣り機で釣り上げます。
イカを夜釣りで漁獲するときに漁船がともす集魚灯は、漁火(いさりび)として有名です。
イカの上手な選び方
- 目が黒く澄んでいて、透明感があるもの。
- 身に弾力がありツヤがあるもの。
- 吸盤に吸着力があるもの。
- ホタルイカは目が黒くすんでいるもの。
- コウイカは肉が厚く、吸盤が吸い付くもの。
- スルメイカは、胴体が茶色や黒のものが新鮮であり、白っぽいものは避けたほうがいいでしょう。
イカの保存法
イカは、冷凍することで組織がくずれるので、やわらかくなり、甘みが増して美味しくなります。
イカを食べやすい大きさに切り、保存袋に入れ、空気を抜いて冷凍するとよく、調理時には冷蔵庫で解凍するといいでしょう。
脂肪が少ないため酸化に強く、冷凍を繰り返しても味や栄養分はそれほど落ちないです。
【イカのカロリーや栄養はコチラ】
▶▶▶イカのカロリー一覧と糖質!栄養や効果なども紹介

